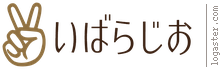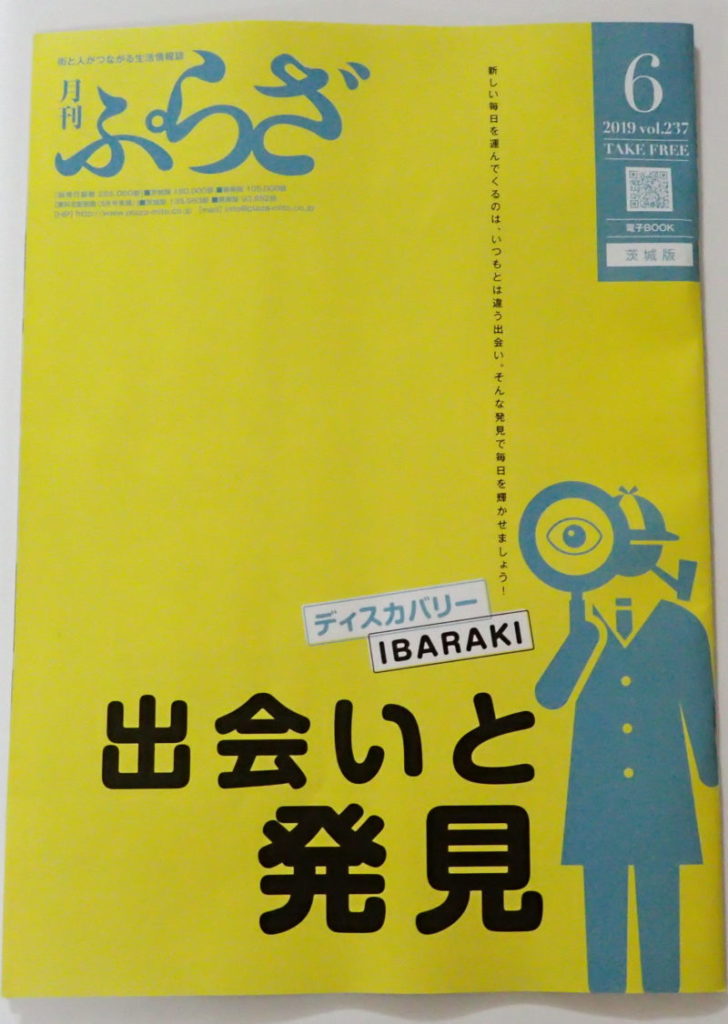茨城の難読地名 を勝手にランキングして紹介します。あなたは全部読めますか?

北の大地、北海道に長万部や愛冠など難読地名があるように、我らが茨城にも他県の人には
ぜってぇ~読めねぇべ!!
って難読地名がいくつかあります。
今回は、そんな茨城の難読地名を勝手にランキングして紹介しますね。
5位 「七五三場」
まずは、茨城県結城市の[七五三場]
これは普通に…「しちごさん…?? 」
いやいや、ぜんぜん違います。場は「ば」と読みますが…
正解は「しめば」です。
七五三場と書いて「しめば」と読むんです!
由来とされる説のひとつは神社などで用いる「しめ縄」。しめ縄にはさまざまな種類があり、その一つに、結った縄から垂らすワラの数を順に3、5、7本とするものがあるらしく。そこで、しめ縄を「七五三縄(しめなわ)」とも書くそうです。結城市の七五三場では神社のしめ縄が盛んに作られていたとか、いないとか…。とにかく絶対に読めねぇべよねw
4位 「手子生」
お次は、茨城県つくば市の[手子生]
これは、ちょっと簡単かも…。ふつうに読めちゃった人も多いかな??
そうです。
正解は「てごまる」です。
これは由来が面白くてですね。とある神社が由来らしいんですよ。
昔々、つくば市のある村に住んでいた若夫婦、夫の留守中にその妻が村の若い衆に“いたずら”されると困るからって隣に住む爺さんが手を当てて守っていたらしいのね。(←よっぽどの美人だったのかな?)
すると、いつしか彼女は妊娠w(←こりゃとんでもない爺さんだっぺよw)
で、生まれた子供がかなりの秀才で、大人になってから立派な功績を残したことから後世その徳を慕って神社を建立し
「手を当ててたら子供が生まれた!(←そんなわけないw)」事から手子生神社と名づけたそうな…。
そんな日本版イエスキリストみたいな伝説が由来なんですね~

3位 「大角豆」
こんどは難易度高め、茨城県つくば市の[大角豆]
これも、もしかしたら読める? と思った人、
だいかど…? おおかど…? なんて読もうとしてたら絶対に読めねぇべよねw
正解は「ささぎ」と読むんです。
実はね、大角豆(ささげ)っていう豆があるんですよ!!(←僕も最近知ったんだけど。)
この大角豆(ささげ)が転じて「ささぎ」になったらしいです。
なんでも大角豆では大角豆の生産が盛んだったとか…そうでもなかったとか。
昨年栽培した #ササゲ で #善哉 を作りました。
#ヨーグルト に入れるのも美味しい!。#家庭菜園 #大角豆 pic.twitter.com/7O5vc3lo9d
— 旅人 (@kakitikao) 2018年7月9日
2位 「随分附」
いよいよ茨城の難読地名、おしくも第2位に選ばれたのは、茨城県笠間市の[随分附]
ん…。この辺にくると漢字自体があんまり見たことないもんね。もうダメ? ギブアップかな? ふつーは読めねーべよねぇ…
はい。これ、
正解は「なむさんづけ」と読むんです。
由来は、目下の人に自分の身分に随(←したが)って、そのつとめを果たすように申しつける「なふさつ」が転じて「なむさんづけ」になったとか。
ほかにも仏教由来説やアイヌ語説など色々あって詳しいことは不明らしいですよ。

1位 「木葉下」
そして、僕が勝手に選ばせてもらった難読地名ランキング、キングオブ茨城の難読地名に輝いたのは…
茨城県水戸市の[木葉下町]
茨城県の難読地名、栄えある第1位は水戸市の「木葉下」です。読みづらい事が名誉なことなのかどうかは分かりませんが勝手に1位に選ばせていただきましたw ちなみに、僕はここにある公園が大好きで子供たちとよく遊びに行きます。
木葉下?? このは…?? いや、これは知らないと絶対に読めません。
正解は「あぼっけ」と読むんです。
木葉下(あぼっけ)の由来はアイヌ語の「o-pok(崖の下)」からきていると地元民のあいだでは言われているようですよ。たしかに木葉下町は山と山の間の谷間みたいな土地ですからね。
さらに木葉下町は、2006年の映画「日本沈没」にて、日本が沈没した際に最後まで残った場所だったことでも有名なんだとか。(←観た事ないから何とも言えないけど、ちょっとカッコイイよねw)
この記事のまとめ
茨城の難読地名 ということで、今回は茨城県の難読地名を勝手にランキングして紹介しました。
まだまだたくさんの難読地名が我が茨城県にはあるんですけど、しょーじき北海道には敵わないかな…
この記事の冒頭で例に挙げた「愛冠」とか皆さん読めますか??
これ、正解は「あいかっぷ」です。
学校のクラスの子にはまだグラビアアイドルなこともIカップなこともバレてません(本当) pic.twitter.com/FIkrNVhsDW
— もものすけ🍑🦖 (@momonosuke1020) June 30, 2024
やっぱり北海道はデッカイ道ですねw
↑愛冠にお住まいの方、はたまた北海道にお住まいの方、たわいのない冗談ですのでお許しを
以上、愛冠と長万部(Iカップとおしゃまんべ)したい清宮真でした。

最新情報をお届けします
Twitter でいばらじお♪をフォローしよう!
Follow @makoto_seimiya